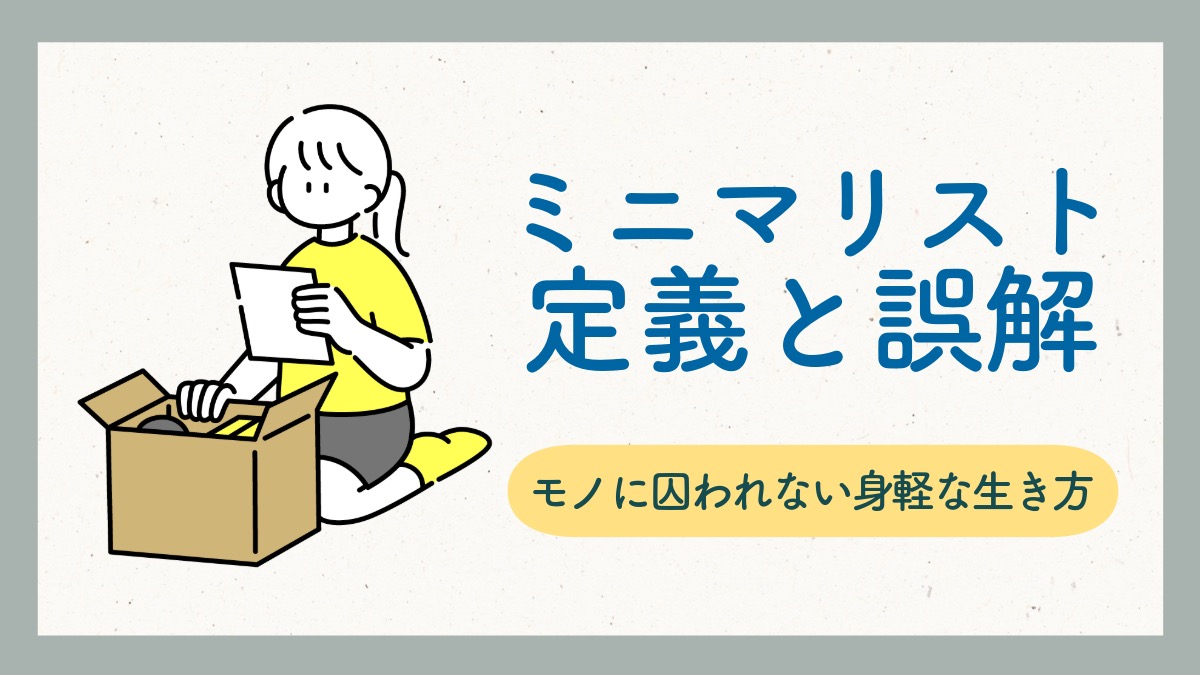【知らないと損】てんかんとは?原因の8割は不明って本当?専門医レベルでわかりやすく解説
もしかして、自分や家族の症状はてんかん…?その不安、この記事で解消します
「てんかん」という言葉を聞いて、あなたはどんなイメージを持ちますか?
「突然、意識を失ってバタッと倒れる病気でしょう?」 「原因もよくわからなくて、治らない難しい病気なんじゃないの?」 「もし自分や大切な家族がなったら、普通の生活はもう送れないのかな…」
こんな風に、漠然とした不安や少し怖いイメージを持っている方が多いかもしれません。特に、ご自身やご家族に気になる症状があってこのページにたどり着いた方は、「てんかんとは一体何なのか、そしてその原因は何なのか」を必死に調べているのではないでしょうか。
その不安、とてもよくわかります。原因がわからないことほど、怖いことはありませんよね。
でも、安心してください。この記事を最後まで読めば、あなたが抱えている「てんかんとは?」「原因は?」という疑問や不安が、スーッと晴れていくはずです。
この記事では、単に専門的な情報を並べるだけではありません。「読者の日常を豊かにする実用的な知のパートナー」として、まるで専門医が隣で優しく語りかけるように、以下のことを徹底的に、そしてどこよりも分かりやすく解説します。
- 多くの人が誤解している「てんかん」の本当の姿
- 気になる「てんかんの原因」の最新情報と、年代別の特徴
- 「もしかして?」と思った時に知っておくべき検査の流れ
- てんかんと上手に付き合っていくための、プロが教える具体的なヒント
この記事を読み終える頃には、「なるほど、てんかんってそういうことだったのか!」「原因がわかって少し安心した」「これからどうすればいいか、道筋が見えた!」と、前向きな気持ちになっていることをお約束します。さあ、一緒に「てんかん」の正体を解き明かしていきましょう。
【結論】てんかんは脳の「電気の火事」!原因は様々だけど、多くはコントロール可能です
今すぐ知りたい!というあなたのために、この記事の結論からお伝えします。
一言でいうと、てんかんとは「脳の神経細胞が突然、過剰に興奮してしまう(ショートしてしまう)ことで、発作を繰り返す病気」のことです。 よく「脳の電気的な嵐」や「電気の火事」に例えられます。
そして、最も気になる「てんかんの原因」ですが、実は原因が特定できないケースが全体の約6割を占めています。 しかし、「原因不明」だからといって絶望する必要は全くありません。
重要なポイントは以下の3つです。
- . 原因は多岐にわたる: 生まれつきの要因から、脳卒中や頭の怪我といった後天的なものまで、てんかんの原因は本当に様々です。 年齢によっても主な原因は変わってきます。
- . 原因不明でも治療は可能: 原因がはっきりしなくても、脳波検査などで診断し、適切な治療を始めることができます。
- . 約7-8割は薬でコントロール可能: てんかんと聞くと「治らない」というイメージが強いかもしれませんが、適切な治療によって約7〜8割の人は発作をコントロールし、普通の社会生活を送ることが可能です。
- 意識が数秒〜数十秒だけ遠のく、ボーっとする(欠神発作)
- 話の途中で急に反応がなくなる
- 一点をじっと見つめて動きが止まる
- 口をもぐもぐさせたり、手をもじもじさせたりする無意味な動作を繰り返す(自動症)
- 体の一部がピクッと動く(ミオクロニー発作)
- 朝、持っている箸やコップを落としてしまう
- 急に吐き気を催したり、お腹が痛くなったりする(自律神経発作)
- 目の前にチカチカした光が見える、変な匂いがする、 déjà vu(既視感)を強く感じる(前兆・焦点発作)
- . 構造的(Structural)要因
- 脳卒中(脳梗塞、脳出血): 特に高齢者でてんかんを発症する最大の原因です。 脳の細胞がダメージを受けることで、電気信号の異常が起きやすくなります。
- 頭部外傷: 交通事故や転落などで頭を強く打った後、数年経ってから発症することもあります。
- 脳腫瘍: 腫瘍が脳を圧迫したり、周囲の神経細胞に影響を与えたりすることで発作を引き起こします。
- 周産期脳障害: 出産時に赤ちゃんが低酸素状態になったり、仮死状態で生まれたりした場合の脳のダメージが原因となることがあります。
- . 遺伝的(Genetic)要因
- . 感染性(Infectious)要因
- . 代謝性(Metabolic)要因
- . 免疫性(Immune)要因
- . 原因不明(Unknown)
- 特発性(原因不明)が約6割: 小児てんかんの半数以上は、現在の検査では明らかな原因が見つからない「特発性てんかん」です。 これらの中には、特定の年齢で発症し、成長とともに自然に治る良性のタイプも多く含まれます。
- 周産期脳障害: 出生時の仮死状態や低酸素などが原因となるケースです。
- 先天性の脳の奇形や代謝異常: 生まれつきの脳の構造の問題や、体の代謝機能の異常が原因となることもあります。この場合、多くは3歳までに発症します。
- 遺伝的要因: 特定の遺伝子変異によるてんかん症候群(ドラベ症候群など)は、乳幼児期に発症することが多いです。
- 頭部外傷: 交通事故やスポーツなどによる頭の怪我が、数年後に原因となることがあります。
- 脳腫瘍: 比較的若い年代での発症の場合、脳腫瘍が隠れている可能性も考えられます。
- 脳炎・髄膜炎などの感染症: 感染症の後遺症として発症するケースです。
- 原因不明: 成人期でも、原因が特定できないケースは少なくありません。
- . 脳卒中(脳血管障害): 高齢者のてんかんの原因として最も多く、全体の30〜40%を占めます。 脳梗塞や脳出血を起こした後に、後遺症としててんかんを発症するパターンです。
- . アルツハイマー病などの認知症(神経変性疾患): 認知症によって脳の神経細胞が変性していく過程で、てんかんを発症することがあります。
- . 脳腫瘍・頭部外傷: 高齢者の場合も、これらの原因が考えられます。
- いつから始まったか?
- どんな症状だったか?(できるだけ具体的に)
- 意識はどうだったか?(呼びかけに反応したか)
- 目の動きは?(一点を見つめる、左右に寄るなど)
- 手足の動きは?(突っ張る、ガクガク震える、左右差はあったか)
- 顔色は?(青ざめる、赤くなるなど)
- 発作の前に何か前兆はあったか?(気持ち悪い、光が見えるなど)
- どのくらい続いたか?(秒単位、分単位で)
- 発作の後はどうだったか?
- すぐに意識は戻ったか?
- ぼーっとしていたか?
- 眠ってしまったか?
- 頭痛や吐き気はあったか?
- どんな時に起こりやすいか?
- 寝起き、寝入りばな、睡眠中?
- 疲れている時、寝不足の時?
- 発熱時?
- 開閉眼: 目を開けたり閉じたりします。
- 光刺激: 目の前で光をチカチカさせます。
- 過呼吸: 深呼吸を数分間繰り返してもらいます。
- CT検査: X線を使って脳の断面を撮影します。脳出血や大きな脳腫瘍などを調べるのに適しています。
- MRI検査: 強力な磁石と電波を使って、より詳細に脳の状態を映し出します。 CTでは見つけにくい小さな脳腫瘍や、生まれつきの脳の構造異常、脳梗塞の跡など、てんかんの原因となりうる様々な病変を発見することができます。
- 薬の飲み忘れ: 最も基本的で最も重要なことです。自己判断で薬をやめたり、不規則に飲んだりすると、発作が再発するリスクが高まります。
- 過度の疲労やストレス: 肉体的、精神的なストレスも発作の引き金になります。
- 飲酒: アルコールは、多くの人で発作を起こりやすくします。飲むとしても、ごく少量に留めるのが賢明です。
- 一部の市販薬: 風邪薬など、薬によっては抗てんかん薬の効果に影響を与えるものがあります。他の薬を飲む際は、必ず主治医や薬剤師に相談しましょう。
- 光刺激(光過敏性てんかんの場合): テレビゲームの激しい光の点滅や、暗い場所でのスマートフォンの強い光などが発作を誘発することがあります。
- . 就寝・起床時間を一定にする: 休日でも、できるだけ平日と同じ時間に起きるようにしましょう。生活リズムを整えることが大切です。
- . 寝る前のスマホ・PCは控える: ブルーライトは脳を覚醒させてしまい、寝つきを悪くします。寝る1時間前からは画面を見るのをやめ、リラックスできる時間を作りましょう。
- . 自分に合ったリラックス法を見つける: 温かいお風呂にゆっくり浸かる、好きな音楽を聴く、軽いストレッチをするなど、心と体をリラックスさせる習慣を取り入れましょう。
- . 病名: 「てんかんという病気を持っています」
- . 症状: 「私の発作は、急にボーっとするタイプで、けいれんはありません」など、具体的に伝える。
- . 対処法: 「発作が起きたら、危険なものから遠ざけて、数分そっと見守っていてください。すぐに治まります。でも、もし5分以上続くようなら救急車を呼んでください」など、してほしいことを明確に伝える。
- . 安全確保: まずは周りの危険なもの(机の角、硬いものなど)を取り除き、頭の下に柔らかいものを敷いて保護します。 衣服の襟元を緩めて呼吸を楽にしてあげましょう。
- . 体をゆすらない、口に何も入れない: 体を押さえつけたり、大声で呼びかけたりしても発作は止まりません。 また、舌を噛むのを防ごうと口にタオルなどを入れるのは、窒息や歯が折れる危険があるので絶対にやめてください。
- . 横向きに寝かせる: けいれんが終わったら、体を横向きにして、唾液や嘔吐物が喉に詰まるのを防ぎます。
- . 様子を観察する: 発作の様子(時間、症状)をよく見ておき、後で本人や医療者に伝えられるようにします。
- . 救急車を呼ぶ目安: ほとんどの発作は数分で収まります。 しかし、①けいれんが5分以上続く場合、②短い間隔で発作を繰り返す場合、③意識がなかなか戻らない場合、④大きなケガをした場合は、ためらわずに救急車を呼んでください。
- てんかんは「脳の電気の火事」: 脳の神経細胞の異常な興奮によって発作を繰り返す病気で、けいれんだけでなく、ボーっとするなど多彩な症状があります。
- 原因は様々、でも「原因不明」も多い: 脳卒中や頭の怪我など原因が明らかな「症候性」と、原因不明の「特発性」があります。 特に小児では原因不明のケースが多いですが、過度に心配する必要はありません。
- 多くは治療でコントロール可能: てんかんは特別な病気ではなく、約100人に1人が持つありふれた病気です。 そして、約7〜8割は薬物治療で発作を抑え、普通の生活を送ることができます。
- 睡眠不足は最大の敵: 規則正しい生活、十分な睡眠、薬の確実な服用が、発作を予防する上で最も重要です。
- 高齢者のてんかんは「認知症」と間違われやすい: ボーっとする、反応が鈍いといった症状は、年のせいではなく治療可能なてんかんのサインかもしれません。
つまり、てんかんは決して「特別な病気」でも「不治の病」でもない、ということです。正しい知識を持ち、専門医のもとで適切な治療を受ければ、過度に恐れる必要はありません。
それでは、ここから一つひとつ、あなたの疑問を解消するために詳しく解説していきますね。
そもそも「てんかん」とは?多くの人が誤解している3つのこと
まずはじめに、多くの人が抱いている「てんかん」に対する誤解を解いていきましょう。ここを理解するだけで、漠然とした不安がかなり軽くなるはずです。
誤解1:突然バタッと倒れるだけがてんかんじゃない!多彩な発作の症状
「てんかん発作」と聞くと、多くの人がドラマのワンシーンのように、突然意識を失って全身をけいれんさせる姿を思い浮かべるかもしれません。もちろん、そういった「強直間代発作(きょうちょくかんだいほっさ)」と呼ばれる発作もてんかんの症状の一つです。
しかし、てんかんの発作はそれだけではありません。脳のどの部分で「電気の火事」が起きるかによって、現れる症状は千差万別なのです。
例えば、以下のような症状もてんかん発作の可能性があります。
SNSでも、「うちの子、ただボーっとしてるだけだと思ってたら、てんかんの欠神発作だった…。もっと早く気づいてあげればよかった」というような投稿を見かけることがあります。
このように、一見するとてんかんとは分かりにくい症状も多いのです。 大切なのは、「てんかん発作=全身けいれん」という固定観念を捨てること。同じ発作を繰り返し起こすのが特徴なので、「あれ?また同じような変な症状が出てるな」と感じたら、専門医に相談するサインかもしれません。
誤解2:「治らない病気」「特別な病気」というわけではない
「てんかんは一生付き合っていく病気」というイメージも根強いですが、これも半分正解で半分誤解です。
確かに、てんかんは慢性的な病気であり、治療を継続する必要がある場合が多いです。 しかし、先ほども述べた通り、適切な薬物治療によって、患者さん全体の約7〜8割は発作を完全に抑えるか、日常生活に支障がないレベルまでコントロールすることが可能です。
また、小児てんかんの中には、成長とともに発作が自然になくなっていく「良性のてんかん」もあります。 一方で、複数の薬を使っても発作を抑えられない「難治性てんかん」の方も約3割いますが、その場合でも外科手術や食事療法、最新の刺激療法など、様々な治療選択肢が開発されています。
さらに、てんかんは決して珍しい病気ではありません。有病率は約100人に1人と言われており、これは日本全国で約100万人もの患者さんがいる計算になります。 つまり、あなたの学校のクラスや職場、ご近所さんの中に、てんかんを持つ人がいても全く不思議ではないのです。決して「特別な人がなる病気」ではありません。
誤解3:遺伝するとは限らない
「自分がてんかんだと、子どもにも遺伝してしまうのでは…」と心配される方は非常に多いです。結論から言うと、てんかんの遺伝性は極めて乏しいと考えられています。
てんかんの原因は後ほど詳しく解説しますが、遺伝子の変異が関係するタイプのてんかんも確かに存在します。 しかし、それはてんかん全体のごく一部です。
具体的なデータを見てみましょう。親がてんかんの場合、その子どもがてんかんを発症する確率は4〜6%程度と言われています。 これは、一般の人の発症率の2〜3倍ではありますが、逆に言えば94%以上の子どもはてんかんを発症しないということです。
多くのてんかんは、遺伝的要因だけでなく、様々な環境要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。 ですから、「てんかん=遺伝する病気」と過度に心配する必要はありません。もしご自身のてんかんのタイプと遺伝について詳しく知りたい場合は、主治医に相談してみるのが一番です。
【本題】てんかんの気になる原因とは?実は「原因不明」がほとんどってホント?
さて、いよいよ本題である「てんかんとは 原因」について深掘りしていきましょう。なぜ、脳の電気的な火事が起きてしまうのでしょうか。
てんかんの原因を大きく2つに分類!「症候性てんかん」と「特発性てんかん」
てんかんの原因は、大きく分けて2つのタイプに分類されます。この2つの言葉を知っておくだけで、医師の説明がグッと理解しやすくなりますよ。
| 分類 | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| 症候性(しょうこうせい)てんかん | 脳に何らかの明らかな原因(病変や傷)があるもの | 脳卒中、頭部外傷、脳腫瘍、脳炎など、原因は様々。 年齢が上がるほどこのタイプの割合が増える。 |
| 特発性(とくはつせい)てんかん | 様々な検査をしても明らかな原因が見つからないもの | てんかんになりやすい体質的な要因(遺伝的素因など)が関係していると考えられている。 子どものてんかんの約6割を占める。 |
簡単に言えば、「原因がはっきりしているか、していないか」の違いです。そして驚くべきことに、子どものてんかんでは約6割、全体でもかなりの割合が、原因不明の「特発性てんかん」に分類されるのです。
「え、原因がわからないのに治療できるの?」と不安に思うかもしれません。でも大丈夫です。特発性てんかんは、むしろ薬が効きやすい良性のタイプが多いことが知られています。 医師は、発作のタイプや脳波のパターンなどから総合的に診断し、最適な治療法を選択していきます。
症候性てんかんの原因となる具体的な6つの要因
では、原因が特定できる「症候性てんかん」には、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。国際抗てんかん連盟(ILAE)が提唱する新しい分類では、原因を6つに分けて考えています。
脳の形や構造に異常がある場合です。これは、生まれつきのもの(脳皮質形成異常など)と、後天的なもの(ケガや病気)に分けられます。
特定の遺伝子の変異が、てんかん発作の起こりやすさに直接関連している場合です。 ただし、前述の通り、これが原因となるてんかんは全体の一部です。
ウイルスや細菌が脳に感染することで起こる「脳炎」や「髄膜炎」の後遺症としててんかんを発症することがあります。
体内の化学反応(代謝)に生まれつき異常があり、脳の神経細胞が正常に働かなくなることで発作が起こる場合があります。
本来は体を守るはずの免疫システムが、誤って自分自身の脳を攻撃してしまう「自己免疫性脳炎」などが原因となるケースです。
現在の医療技術では、上記のいずれにも当てはまらない、原因が特定できないものを指します。これが従来の「特発性てんかん」の多くを含みます。
このように、「てんかんの原因」と一口に言っても、非常に多岐にわたることがお分かりいただけたかと思います。
「プロならこう見る!」原因究明の最前線と最新の考え方
ここで少し、プロの視点からのお話をさせてください。私が研修医だった頃、先輩医師から「てんかんの診断は、刑事の捜査と同じだ」と教わりました。
患者さんの話(問診)、発作の目撃情報、そして脳波やMRIといった物的証拠を一つひとつ丁寧に集め、犯人、つまり「てんかんの原因」を追い詰めていく。このプロセスが非常に重要なんです。
昔は「症候性」か「特発性」かの二元論で語られることが多かったのですが、最近は研究が進み、その境界線は曖昧になってきています。
例えば、以前は「特発性(原因不明)」とされていたてんかんの中に、遺伝子解析技術の進歩によって、特定の遺伝子変異が見つかるケースが増えてきました。 また、一見すると脳に異常がないように見えても、特殊なMRIを撮影すると、ごく微細な脳の構造異常(犯人の隠れ家!)が見つかることもあります。
つまり、「原因不明」というのは、あくまで「現在の医療では原因を特定できない」という意味であり、将来的には原因が解明される可能性を秘めているのです。原因が特定できれば、より根本的な治療法(例えば、特定の遺伝子に作用する薬など)の開発に繋がるかもしれません。実際に、てんかん治療の研究は日進月歩で進んでいます。
私たち医師は、「原因不明だから仕方ない」と諦めるのではなく、常に最新の知見を取り入れながら、患者さん一人ひとりの「なぜ?」に真摯に向き合っています。
年齢別で見る「てんかんの原因」こんなに違う!乳幼児から高齢者まで徹底解説
てんかんは、どの年代でも発症する可能性がありますが、実は発症のピークは2回あります。1つは3歳以下の乳幼児期、そしてもう1つは60歳以上の高齢期です。 そして、年代によって主な原因が大きく異なるのが特徴です。
赤ちゃん・子供(小児てんかん)に多い原因
お子さんのてんかんは、親御さんにとって最も心配なことの一つだと思います。小児てんかんの原因は多岐にわたりますが、成人とは異なる特徴があります。
小児期は脳が発達するとても大切な時期です。 発作を繰り返すことで発達に影響が出る可能性もあるため、気になる症状があれば早めに小児神経科医などの専門医に相談し、適切な診断と治療を受けることが非常に重要です。
成人期に発症する場合の主な原因
18歳以降の成人期に初めててんかんを発症する場合、小児期とは少し原因が異なってきます。
高齢になってから発症するてんかんの原因トップ3
近年、特に注目されているのが「高齢者のてんかん」です。65歳以上になると、てんかんの発症率は再び増加します。
ここで非常に重要なポイントがあります。それは、高齢者のてんかん発作は、ボーっとしたり、反応が鈍くなったりする症状が多く、けいれんを伴わないことが多いため、「認知症」や「年のせいによる物忘れ」と間違われやすいということです。
ご家族が「最近、急にぼーっとすることが増えた」「話が噛み合わない時がある」と感じていたら、それは認知症ではなく、治療可能な「てんかん」の症状かもしれません。 実際に、認知症と診断されていた患者さんが、実はてんかんで、抗てんかん薬の治療を始めたら症状が劇的に改善した、というケースも少なくないのです。
もしかして、てんかんかも?と思ったら…最初に知っておくべき検査と診断の流れ
「うちの子のこの症状、もしかして…」「最近、時々意識が飛ぶことがある…」 もし、あなたやご家族にてんかんを疑う症状があれば、まずは専門医(脳神経内科、脳神経外科、精神科、小児の場合は小児神経科)を受診することが第一歩です。ここでは、病院で行われる主な検査の流れを、不安が少しでも和らぐように解説しますね。
問診で聞かれることリスト(これだけは準備しておこう!)
てんかんの診断において、実は最も重要なのが「問診」です。 医師は、あなたやご家族からの情報をもとに、発作の正体を探っていきます。なぜなら、発作そのものを医師が直接目撃できることは稀だからです。
受診する前に、以下の点をメモにまとめておくと、診察がスムーズに進み、より正確な診断に繋がります。
【プロの視点】
もし可能であれば、発作の様子をスマートフォンなどで動画撮影しておくことは、非常に有力な情報になります。 百聞は一見にしかずで、動画を見れば一目瞭然なことも多いのです。ためらわずに、医師に見せてください。
脳波検査って何するの?痛い?怖くない?
てんかんの診断に欠かせないのが「脳波検査」です。 これは、脳の微弱な電気活動を頭皮に付けた電極でキャッチし、波形として記録する検査です。
「頭に電気を流すの?痛くない?」と心配される方もいますが、全く逆です。脳から出ている電気信号を受け取るだけなので、痛みや刺激は一切ありません。 髪の毛にクリーム状のペーストで電極を付けていくだけです。
検査中は、ベッドに横になってリラックスしてもらいます。途中で、以下のような刺激を与えて、脳波の変化を見ることがあります。
また、てんかんの異常な波(専門的には「てんかん性異常波」と言います)は、起きている時よりも眠っている時に出やすいことがあります。 そのため、検査中に少し眠ってもらうこともあります。特に小さなお子さんの場合は、少し眠くなるお薬を使って検査をすることもあります。検査時間は通常1時間前後です。
ただし、1回の脳波検査で異常が見つからないことも珍しくありません。 その場合は、日を改めて検査を行ったり、入院して長時間の脳波を記録したりすることもあります。
画像検査(CT・MRI)で何がわかるのか
脳波検査と並行して、脳の形や構造に異常がないかを調べるために、CTやMRIといった画像検査を行うことがよくあります。 これは、特に「症候性てんかん」の原因を探るために重要です。
これらの検査結果を総合的に判断して、医師は「てんかんかどうか」「てんかんだとしたら、どのタイプか」「原因は何か」を診断し、一人ひとりに合った治療方針を決めていくのです。
てんかんの原因と日常生活での付き合い方|プロが教える5つのヒント
てんかんと診断されたら、治療と並行して大切になるのが日常生活でのセルフケアです。発作はきっかけなく起こることも多いですが、特定の状況で起こりやすくなることもあります。 ここでは、てんかんと上手に付き合っていくための具体的なヒントを、失敗談やSNSの声も交えながらご紹介します。
失敗談から学ぶ!発作を誘発しやすいNG行動とは?
てんかんの発作を起こしやすくする要因(誘発因子)は人によって様々ですが、多くの人に共通するものがあります。 ここでは、ある患者さん(Aさん、20代男性)の創作エピソードを通じて、やりがちな失敗を見てみましょう。
> Aさんは、数年前にてんかんと診断され、薬を飲んでいれば発作はほとんど起きていませんでした。ある週末、友人とオンラインゲームに夢中になり、気づけば朝に。そのままほとんど眠らずに出かけたところ、駅のホームで意識を失う発作を起こしてしまいました。幸い大きなケガはありませんでしたが、あと一歩で線路に転落するところでした。「薬を飲んでるから大丈夫」という油断と、たった一晩の徹夜が、大きな事故に繋がりかねない事態を招いてしまったのです。
このAさんのように、睡眠不足はてんかん発作の最大の誘発因子の一つです。 その他にも、以下のような点は注意が必要です。
薬との上手な付き合い方「飲み忘れ」を防ぐ意外な工夫
抗てんかん薬は、発作を抑えるためのいわば「お守り」です。毎日決まった時間に飲むことが何より大切。 でも、忙しい毎日の中でつい忘れてしまうこともありますよね。
SNSで見つけた、皆さんが実践している飲み忘れ防止の工夫をいくつかご紹介します。
> 「100均のピルケースに曜日シールを貼るのは定番だけど、私はそれに加えて好きなアイドルのシールを貼ってる!推しに見守られてる感があって、飲むのがちょっと楽しくなるよ笑
てんかん #服薬管理」
> 「スマホのリマインダーアプリ必須!しかもスヌーズ機能付きで、飲むまでしつこく教えてもらう設定にしてる。家族にも協力してもらって、『薬飲んだ?』ってLINEしてもらうのも効果的」
> 「旅行の時は、薬を日数分+予備を必ず持っていく。万が一落としたりしても大丈夫なように、スーツケースと手持ちのバッグに分けて入れてる」
このように、自分なりに楽しく、確実に続けられるルールを作ることが長続きのコツです。もし薬を飲み忘れた場合は、気づいた時点ですぐに1回分を飲みましょう。ただし、次の服用時間に近い場合は、主治医の指示に従ってください。
睡眠不足は最大の敵!質の高い睡眠をとるための3つのコツ
先ほどのAさんの例でも分かる通り、睡眠はてんかんのコントロールに非常に重要です。 成人なら6〜8時間、子どもなら8〜10時間程度の睡眠を目安に、規則正しい生活を心がけましょう。
質の高い睡眠をとるための具体的なコツは以下の通りです。
ストレスとどう向き合う?SNSで見つけた共感の声
ストレスがゼロの生活は難しいですが、上手に発散する方法を見つけておくことは、発作の予防に繋がります。
> 「仕事で大きなミスをして落ち込んでたら、その夜に軽い発作が…。やっぱりストレスって良くないんだなと実感。最近は、意識的に週1で何もしない日を作って、好きなだけゴロゴロしてる。これが私のストレス解消法」
> 「病気のことを話せる友達がいるだけで、すごく気持ちが楽になる。一人で抱え込まないのが一番大事だと思う。
てんかん #ストレス」
趣味に没頭する、スポーツで汗を流す、信頼できる人に話を聞いてもらうなど、あなたに合った方法でストレスを溜め込まないようにしましょう。
周りの人にどう伝える?カミングアウトのタイミングと伝え方の例文
てんかんであることを、学校や職場など周りの人に伝えるべきか、悩む方も多いと思います。これは非常にデリケートな問題で、正解はありません。
しかし、もしもの時に適切な対応をしてもらうためには、信頼できる人や、一緒にいる時間が長い人には伝えておく方が安心です。伝える際は、以下の3点をセットで話すのがおすすめです。
【伝え方の例文(職場の上司へ)】
「ご相談があるのですが、実は私にてんかんという持病があります。薬でコントロールできているので普段の業務に支障はありません。ただ、極度の寝不足や疲労が重なると、稀に数分間ボーっとする発作が起きることがあります。もしそのような状況になりましたら、危険がないように見守っていただけると助かります。体調管理には十分気をつけますので、今後ともよろしくお願いいたします。」
勇気がいることですが、伝えることで周りの理解が得られ、働きやすい環境に繋がることもあります。
てんかんの原因に関するよくある質問(Q&A)
最後に、てんかんの原因に関してよく寄せられる質問にお答えします。
Q. てんかんは遺伝しますか?
A. 前述の通り、多くのてんかんは明確な遺伝形式をとらず、遺伝する可能性は低いと考えられています。 親がてんかんだからといって、子どもが必ずてんかんになるわけではありません。 その確率は4〜6%程度です。
Q. ワクチンが原因になることはありますか?
A. 予防接種が直接てんかんの原因になるという科学的根拠は確立されていません。以前はてんかんがあると予防接種に慎重な時期もありましたが、現在では発作がコントロールされていれば、基本的にどの予防接種も問題ないとされています。 不安な場合は、主治医とよく相談してください。
Q. 食生活や生活習慣はてんかんの原因になりますか?
A. 不規則な食生活や特定の食べ物が直接てんかんの原因になることは通常ありません。 ただし、発作を誘発する要因として、睡眠不足、過労、ストレス、飲酒などは大きく関係します。 規則正しい生活を送ることが、発作の予防に繋がります。
Q. てんかん発作が起きたら周りの人はどうすればいいですか?
A. もし目の前で誰かが発作を起こしたら、慌てず、落ち着いて対応することが大切です。
【けいれんを伴う発作の場合】
【ボーっとする発作の場合】
無理に動きを止めようとせず、危険がないように優しく見守り、付き添ってあげてください。
正しい知識を持つことが、本人にとっても周りの人にとっても一番の安心に繋がります。
まとめ:正しい知識が、あなたと大切な人を守る第一歩です
今回は、「てんかんとは 原因」をテーマに、多くの人が抱く誤解から、原因の最新情報、年代別の特徴、そして日常生活での付き合い方まで、徹底的に解説してきました。最後に、この記事の重要なポイントをもう一度確認しましょう。
てんかんに対する漠然とした不安や恐怖は、その正体を知らないことから生まれます。この記事を読んで、てんかんという病気を正しく理解できたことで、あなたの心は少し軽くなったのではないでしょうか。
もし、あなたやあなたの大切な人が「もしかして?」と感じているなら、一人で悩まずに専門医に相談してください。正しい知識は、あなたとあなたの周りの人を守る最強の武器になります。今日得た知識を、ぜひこれからの人生に役立ててください。