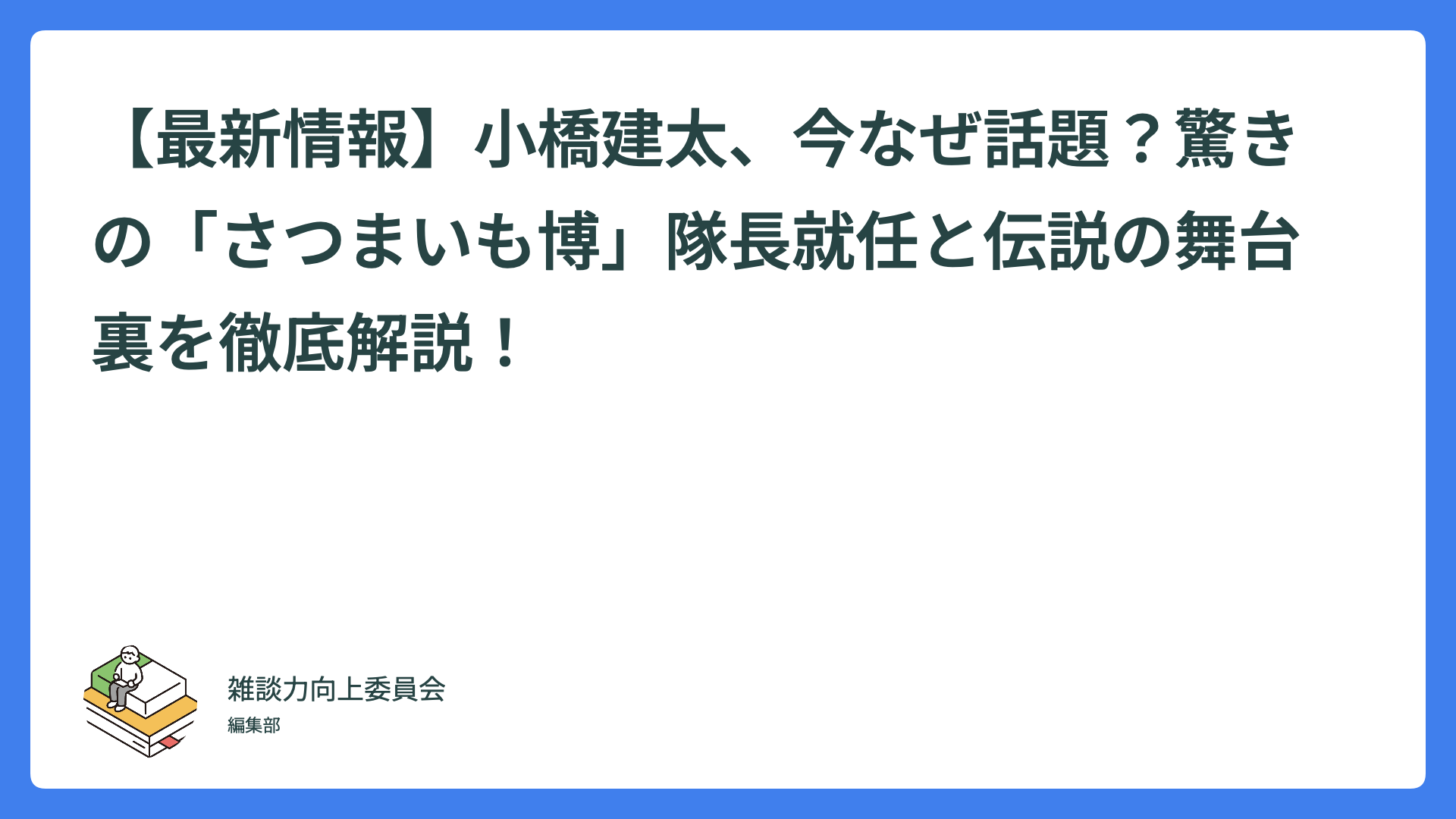速報!小田急が驚愕進化!2025年「ダイヤ改正」「子育て応援車」が描く未来【知らないと損する大変革】
はじめに
今、「小田急」というキーワードが、多くの人々の間で注目を集めていることをご存知でしょうか。単なる鉄道会社の枠を超え、小田急電鉄は2025年に、利用者体験を劇的に向上させるための大規模な変革を次々と打ち出し、その進化はまさに「驚愕」の一言に尽きます。通勤・通学の日常風景から、週末のレジャー、子育て世代の移動まで、私たちの生活に密接に関わる小田急線が、なぜ今これほどまでに話題となり、検索されているのか。それは、2025年3月の歴史的なダイヤ改正にはじまり、「子育て応援車」の導入、総額436億円にも上る設備投資、そして秋以降に拡大される画期的なタッチ決済システムなど、まさに「知らないと損する」価値ある情報が満載だからです。この記事では、これらの最新ニュースを徹底深掘りし、小田急が描く未来の姿とその背景を余すことなくお伝えします。
—
2025年3月ダイヤ改正の衝撃と利便性革命
2025年3月15日、小田急線全線で実施されたダイヤ改正は、通勤客から観光客まで、あらゆる利用者に大きな影響を与える「利便性革命」とも呼べるものでした。 この改正は、現行ダイヤをベースとしつつも、利用者のニーズに合わせたきめ細やかな変更が加えられ、よりスムーズで快適な移動の実現を目指しています。
特急ロマンスカーの増発と延伸で広がる選択肢
今回のダイヤ改正で特に注目すべきは、特急ロマンスカーの運行体制が大きく見直された点です。 平日の夜間、特に仕事帰りやレジャーからの帰宅時に重宝される「ホームウェイ号」(下り列車)は、22時台の新宿発の列車が1本増発され、現行の2本から3本へと拡大されました。 これは、満席率が高かった22時台の混雑緩和と、より多くのビジネスパーソンがゆったりと自分時間を過ごせるようにという小田急の配慮がうかがえます。
さらに、土休日には新宿発小田原行きの「さがみ61号」が、同時間帯の新宿発箱根湯本行きの「はこね号」として運転区間を延伸しました。 これにより、箱根観光を終えた利用者は小田原での乗り換えの手間なく、新宿まで直接帰れるようになり、旅の余韻を一層楽しむことができるようになりました。 意外にも、観光客だけでなく、箱根エリアへのアクセスを重視するビジネス利用客にとっても、この延伸は大きなメリットとなるでしょう。
停車駅見直しで広がるアクセスと乗換負担の軽減
ダイヤ改正では、特急列車だけでなく、通勤・通学に欠かせない列車種別ごとの停車駅も見直されました。 小田原線では、喜多見駅と和泉多摩川駅が準急停車駅に追加され、これにより東京メトロ千代田線直通の準急列車が、経堂駅から下り方面の全駅に停車するようになり、特に夕方の帰宅時間帯において、成城学園前駅での乗り換えが不要になるという嬉しい変化が生まれました。
また、多摩線では、五月台駅、黒川駅、はるひ野駅が急行停車駅に変更されました。 これにより、小田原線と多摩線を直通する急行列車がすべてこれらの駅に停車するようになり、新百合ヶ丘駅での乗り換えが不要に。 例えば、新宿から黒川まで乗り換えなしで最速35分で到着するなど、速達性が大幅に向上し、多摩線沿線の利便性が飛躍的に高まりました。 驚くべきことに、これまで一部列車で実施されていた小田原線と多摩線を直通する際の「急行」から「各駅停車」への種別変更が廃止され、分かりやすさも格段に向上しています。
さらに、快速急行が新たに開成駅に停車するようになったことも見逃せません。 これまで快速急行を利用する際には新松田駅で急行に乗り換える必要があった区間が、一部列車を除き乗り換え不要となり、よりスムーズな移動が実現しました。 これらの変更は、日々の通勤・通学のストレス軽減に直結するだけでなく、沿線地域の価値向上にも寄与するでしょう。
混雑緩和への挑戦とリアルタイム情報活用
小田急線といえば、かつて「通勤ラッシュ時の混雑」が課題として挙げられることもありました。 しかし、今回のダイヤ改正では、混雑平準化に向けた具体的な施策も講じられています。 平日夕方の東京メトロ千代田線からの直通準急列車5本が、より停車駅の少ない急行に種別変更されました。 この急行列車は、下り列車の密度が高まる新百合ヶ丘駅で、列車の遅れを生じにくくするために3番ホーム(多摩線ホーム)に停車する工夫が凝らされています。 これにより、遠距離利用で速達性を重視する利用者の代々木上原駅での乗り換えが不要となり、同駅ホームと快速急行の混雑緩和にも繋がり、結果として列車遅延の防止効果も期待されています。
実は、小田急電鉄は以前から朝方ラッシュ時の混雑緩和のため、オフピーク利用を推奨しており、公式アプリ「小田急アプリ」では「列車のリアルタイムご利用状況」や「列車の混雑予報」を配信しています。 このようなデジタル技術の活用とダイヤ改正による運行体制の最適化が相まって、より快適な乗車環境が提供されつつあるのです。
—
ロマンスカーに新風!「子育て応援車」誕生で広がる安心
小田急電鉄が「子育てしやすい沿線」を目指すという強い意志を示す画期的な取り組みとして、2025年4月15日から特急ロマンスカー全編成の3号車が「ロマンスカーの子育て応援車」として運用を開始しました。 このサービスは、子育て世代の保護者とそのお子さまが、より気兼ねなく、そして安心してロマンスカーを利用できるよう、特別な配慮が凝らされたものです。
「子育て応援車」運用の開始とその目的
「ロマンスカーの子育て応援車」は、平日・土休日ともに新宿駅を11時00分から16時59分までに出発する列車と、新宿駅へ11時00分から17時59分までに到着する予定の列車で運用されます。 小田急線・箱根登山線内でのみ実施されますが、この時間帯は特に小さなお子さま連れの家族が観光地へ出かける際や、レジャーから帰宅する際に利用しやすいよう設定されています。
この応援車の最大の目的は、子育て世代が周囲に気兼ねなく、快適に移動できる環境を提供することです。 実は、小田急は2021年11月から「子育て応援ポリシー」を掲げており、この取り組みはそのポリシーのさらなる深化を象徴するものです。
「もころん」デザインと見守り促進の工夫
「ロマンスカーの子育て応援車」の最大の特徴は、小田急電鉄の子育て応援マスコットキャラクター「もころん」が随所にデザインされている点です。 3号車の客室扉脇には「もころん」のステッカーが掲出され、応援車であることを分かりやすく示しています。 さらに、座席には「もころん」が刺繍された専用のヘッドレストカバーが設けられ、車内空間全体で子育て応援の雰囲気を醸し出しています。
これらのデザインは、単にかわいらしいだけでなく、周囲の利用客に対して子育て世代を見守るようにというメッセージを伝える役割も果たしています。 券売機やオンラインで対象列車の3号車を予約・購入する際にも、子育て応援車であることが案内され、安心して座席を確保できる仕組みになっています。 驚くべきことに、この「もころん」は、LINEヤフーが2025年にヒットすると予測した10のアイテムの一つに選ばれるほどの人気ぶりで、小田急の子育て応援のシンボルとして世代を超えて親しまれています。 ロマンスカーの3号車付近には、ほとんどの車型でベビーベッドを備えたお手洗いや自動販売機も用意されており、お子さま連れでの移動に必要な設備が整えられています。
子育て応援ポリシーの深化とイベント展開
小田急電鉄は、この「ロマンスカーの子育て応援車」の導入以前から、子育て世代に寄り添う様々な施策を実施してきました。 その代表例が、小児IC運賃の全区間一律50円化です。 これは、お子さま連れでの鉄道利用の心理的・経済的負担を大きく軽減するもので、多くの親から支持されています。また、主要な駅には完全プライベート空間となるベビーケアルームが14駅に設置されており、おむつ替えや授乳など、人目を気にせず利用できる環境が整備されています。
さらに、小田急グループは、お子さまの成長に寄り添うイベントも積極的に展開しています。 例えば、2024年末には海老名中央公園で、川崎市をはじめとする沿線自治体や企業、鉄道会社が参加する「おだきゅうFamily Fun フェスタ2024」が開催され、鉄道ファンだけでなく多くの親子連れで賑わいました。 運転体験やグッズ販売、スタンプラリーなど、親子で楽しめるコンテンツが多数用意され、地域との連携を通じて子育て世代を応援する姿勢が明確に示されています。 「小田急親子鉄道ゼミ」や、小田急グループやパートナー企業が協力して仕事やスポーツを体験できる「親子体験イベント」なども随時開催され、「Fun Fan おだきゅう」という子育て応援ナビで情報発信されています。 これらの取り組みは、単に鉄道の利用者数を増やすだけでなく、沿線の人口増加や地域活性化、ひいては持続可能なまちづくりにも繋がるという小田急の強い期待が込められています。
—
総額436億円!2025年度鉄道設備投資で「安全」と「快適」を両立
小田急電鉄は2025年5月、2025年度の鉄道事業設備投資計画を発表しました。 その投資総額は驚くべきことに436億円に上り、これは「安全対策の強化」と「サービスの向上」という二つの柱を強力に推進し、鉄道事業の持続的な進化を目指す小田急の覚悟を示すものです。
大規模耐震補強と自然災害への備え
大規模地震や激甚化する自然災害への備えは、鉄道会社の最重要課題の一つです。小田急は、2025年度の設備投資において、鉄道施設の耐震補強工事を重点的に実施します。 具体的には、世田谷代田駅から登戸駅間の高架橋や、読売ランド前駅、相武台前駅、座間駅、長後駅のホーム上家などで耐震補強に着手します。
さらに、2024年度の豪雨によって盛土のり面が崩壊した東海大学前駅から秦野駅間の当該箇所では、早期の補強工事を進めることで、自然災害に対する脆弱性を克服し、安全な運行を確保するとしています。 これらの対策は、利用者が安心して小田急線を利用できる基盤を強化するものであり、まさに「縁の下の力持ち」とも言える重要な投資です。
ホームドア整備の加速で利用者の安全を確保
ホームからの転落や列車との接触事故防止は、駅の安全対策において不可欠な要素です。小田急電鉄は、鉄道駅バリアフリー料金制度や東京都の「ホームドア整備加速緊急対策事業」による補助金などを積極的に活用し、ホームドアの設置を加速させています。
2025年度中には、豪徳寺駅、千歳船橋駅、祖師ヶ谷大蔵駅、喜多見駅、狛江駅の計10ホームでホームドアの使用を開始する予定です。 さらに、経堂駅や和泉多摩川駅など、まだホームドアが整備されていない駅でも、設置に向けた準備が進められています。 また、防犯カメラの設置も進められており、2025年度末までに計画した全車両への設置が完了することで、車内環境の安全性も向上します。 これらの取り組みは、利用者だけでなく、駅で働くスタッフの安全確保にも繋がり、より安心な鉄道空間の創出に貢献します。
新型車両導入と駅改良の進捗で快適性を向上
安全対策に加えて、小田急はサービスの向上にも注力しています。2025年度には、新型通勤車両「5000形」の1編成(10両)が新たに導入される予定です。 5000形は、広々とした明るい車内空間が特徴で、大型強化ガラスを採用した仕切り扉や荷棚、座席横の袖仕切り部、天井埋め込み形のLED照明などにより、開放感と快適性を両立しています。 また、全車両に車いすやベビーカーを利用する乗客のためのスペースが設けられており、誰もが快適に利用できるユニバーサルデザインが追求されています。
さらに、既存の通勤車両「3000形」についても、2編成(6両編成)のリニューアルが実施されます。 こちらも5000形と同様に、全車両に車いすやベビーカー用のスペースが設置され、より多くの方にとって利用しやすい車両へと改修されます。 リニューアル後の3000形に搭載される防犯カメラは、運輸司令所など離れた場所からリアルタイムで映像を確認できる機能を備えており、緊急時における迅速な対応や正確な状況把握が可能になります。
駅改良工事では、鶴川駅と藤沢駅の駅舎が橋上化される予定です。 これらの駅改良は、地元自治体との連携による自由通路整備事業に合わせて行われ、駅周辺の回遊性や利便性が大幅に向上すると期待されています。
—
キャッシュレス時代を加速!タッチ決済・QR認証の全線拡大
2025年秋以降、小田急グループの交通機関で、私たちの移動体験がさらにスマートで便利に進化します。 クレジットカードやデビットカードによるタッチ決済が大幅に拡大されるほか、デジタルチケットのQRコード認証も利用範囲が広がるという画期的なサービスが導入されるのです。これは、まさにキャッシュレス時代の到来を告げる、鉄道業界の新たなトレンドとなるでしょう。
2025年秋からの本格導入で広がる利便性
これまでは一部の路線や交通機関で限られた導入に留まっていたタッチ決済が、2025年秋以降、小田急グループの多岐にわたる交通機関で利用可能となります。 具体的には、小田急線全駅に加え、箱根登山電車、箱根登山ケーブルカー、箱根登山バス、小田急ハイウェイバス、東海バスの一部エリア、そして大山ケーブルカーといった主要な交通機関が対象となります。
このサービスは、三井住友カードの公共交通機関向けソリューション「stera transit」を決済基盤として採用しており、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯といった主要な国際ブランドに対応します。 これにより、乗車券を購入したり、ICカードにチャージしたりする手間なく、普段使いのクレジットカードやデビットカードを改札機や車載リーダーにタッチするだけで、スムーズに乗り降りできるようになります。
さらに、小田急グループが提供するデジタルチケットアプリ「EMot」で発行されるデジタルチケットも、QRコードによる改札通過が可能となる範囲が拡大されます。 事前にスマートフォン等で取得したQRコードを自動改札機や簡易改札機に読み取らせることで、非接触での乗降が可能となり、デジタルフリーパスによる都心部から観光エリアへの移動が、これまで以上に便利になります。
インバウンド誘致と地域活性化への貢献
このタッチ決済・QR認証の拡大は、急速に回復し拡大しているインバウンド需要への対応という側面も持ち合わせています。 2025年4月には訪日外国人数が単月で過去最高の390万人を突破するなど、日本の観光地は活況を呈しています。 小田急沿線に位置する箱根、湘南(藤沢市、鎌倉市)、大山(伊勢原市)といった観光地の年間来訪者数は約5,300万人にも上り、インバウンド誘致は小田急グループの重要な経営戦略の一つです。
海外からの観光客にとって、日本の複雑な交通運賃体系や切符の購入方法はしばしば障壁となっていました。しかし、タッチ決済が普及することで、彼らは手持ちのクレジットカードでそのまま公共交通機関を利用できるようになり、移動のストレスが大幅に軽減されます。 これは、観光客の利便性向上に直結するだけでなく、観光地の周遊促進にも繋がり、結果として地域経済の活性化にも大きく貢献するでしょう。 小田急は、このような最新の決済システム導入を通じて、観光客の受け入れ体制を強化し、より多くの人々が沿線地域を訪れるきっかけを創出することを目指しています。
—
背景・経緯:小田急が挑む持続可能な沿線価値創造
小田急電鉄が2025年にこれほど大規模な変革を次々と打ち出す背景には、日本の社会構造の変化と、それに対応する企業の経営戦略の転換があります。単に鉄道を運行するだけでなく、「沿線全体の生活価値を創造する企業」へと進化しようとする小田急の強い意志がそこには見て取れます。
経営戦略と沿線活性化への強い意志
従来の私鉄のビジネスモデルは、鉄道・バスなどの交通事業を核に、沿線に住宅やレジャー施設を開発し、人口増加を背景に輸送力を増強するというものでした。 しかし、日本全体で少子高齢化が進行する中で、このモデルは転換期を迎えています。 小田急電鉄は、2025年度から2026年度までの中期経営計画において、「安全対策の強化」と「サービスの向上」を重点施策に据え、持続的な成長を目指す方針を明確にしています。
特に、観光事業をグループ全体の「稼ぐ力」の源泉と捉え、箱根や湘南エリアへの投資を強化しています。 小田急の鈴木滋社長は「箱根には長年にわたり投資を継続しており、今後も観光をグループの成長エンジンとして展開していく」と語っています。 「子育て応援ポリシー」に代表されるように、小田急は子育てしやすい沿線環境を整備することで、沿線への定住人口を増やし、地域を活性化させる「地域共創」にも力を入れています。 海老名市では、2000年から2024年の間に人口が約20%増加しており、これは神奈川県全体の増加率(約9%)を大きく上回るなど、小田急の沿線開発が地域成長に寄与している実例もあります。
労働人口の減少という社会課題を見据え、2035年度には2020年度比で要員30%削減を目指すなど、ワンマン運転の導入や駅業務の省力化といった効率化も推進しています。 これは、単なるコスト削減だけでなく、限られた人的資源をより付加価値の高いサービスに振り向け、顧客満足度を向上させる狙いがあると考えられます。
新宿再開発プロジェクトの壮大なビジョン
小田急が現在進行形で推進している「新宿駅西口地区開発計画」も、その未来を見据えた壮大なプロジェクトです。 小田急百貨店新宿店本館の跡地を中心としたこの再開発は、地上48階建て、高さ約258mの超高層複合ビル(A区)と、小田急電鉄が単独で開発する地上8階建ての商業・駅施設(B区)から構成されます。
このプロジェクトは、単なるビルの建て替えに留まらず、東京都や新宿駅周辺の鉄道事業者5社(JR東日本、京王電鉄、東京メトロ、西武鉄道)と連携し、「新宿グランドターミナル」として一体的な開発を進めるものです。 新宿西口は、小田急線の起点であり、1960年代に小田急百貨店や西口広場を中心に小田急がまちづくりを進めてきた歴史を持つ、小田急にとって特別な場所です。
再開発のキーワードは「ビジネス創発」です。 新宿が持つ多様な人々が集まる特性を活かし、企業がリードするのではなく、まちを訪れるユーザーと共に新しい価値を創造できるまちを目指しています。 低層部には商業機能やビジネス創発機能、さらには小田急沿線や東京メトロ沿線の情報発信機能も導入され、新宿が持つ旺盛な消費ニーズを満たしながら、ここでしか得られない新たな体験を提供することを目指しています。 2024年5月に着工し、2029年度の竣工を予定しているこのプロジェクトは、新宿を国際競争力のある魅力的なまちへと生まれ変わらせる、まさに未来への投資と言えるでしょう。
—
関連情報・雑学:小田急の「今」をさらに深掘り
小田急の最新動向は、単なるダイヤ改正や設備投資にとどまりません。未来の移動を支える新型車両の計画や、観光地の新たな魅力創出、さらには歴史的なライバルとの競争の行方まで、多岐にわたるトピックが注目されています。
新型ロマンスカー、2028年度登場へ! VSE後継と展望席への期待
小田急電鉄は、2027年4月の小田急線開業100周年を記念し、2024年9月から「新型ロマンスカー」の設計に着手したことを発表しています。 運行開始は2029年3月(2028年度)を予定しており、これは2023年に惜しまれつつ引退した「VSE」(50000形)の後継車両として位置づけられています。
新型ロマンスカーは、現行の「EXE」(30000形)の代替も担うことになりますが、VSEの後継という位置づけから、多くのファンが「展望席」の復活に大きな期待を寄せています。 VSEは前面展望席が最大の魅力であり、その開放感あふれる車窓は多くの利用者を魅了してきました。 新型車両がどのようなデザインになるのか、展望席がどのような形で実現されるのか、小田急ロマンスカーブランドを継承しながら「一層上質な移動時間」を提供できる車両がどのような姿で登場するのか、今後の情報公開が待たれます。
箱根に新名所「ちきゅうの谷」オープン! 大涌谷の魅力を再発見
小田急グループが長年にわたり観光事業に力を入れている箱根エリアでも、2025年春に新たな魅力が誕生しました。2025年4月25日、箱根ロープウェイの大涌谷駅1階と駅前広場がリニューアルされ、新展望エリア「ちきゅうの谷」がオープンしたのです。
「ちきゅうの谷」は、約3000年にわたる火山活動が生み出した大涌谷のダイナミックな自然を五感で体感できる施設です。 噴煙が立ち上る迫力ある景観を背景に、360度の風を全身で感じられる「風の輪テラス」や、火山地形を間近で望める「息吹のデッキ」、軽飲食を楽しみながらくつろげる「岩の巣ベンチ」などが整備され、大自然との一体感を味わえる工夫が凝らされています。
2025年は、箱根ロープウェイ全線開通と、箱根登山電車、箱根登山ケーブルカー、箱根ロープウェイ、箱根海賊船、箱根登山バスが繋ぐ「箱根ゴールデンコース」の開通65周年という記念すべき年でもあります。 「ちきゅうの谷」の開業は、この節目を飾る一大イベントであり、箱根観光の新たな目玉として、より多くの国内外の観光客を惹きつけることが期待されています。
「箱根山戦争」再燃? 西武との競争の行方
日本有数の観光地である箱根では、実は歴史的に小田急グループと西武グループの間で激しい企業間競争が繰り広げられてきました。 1950年代から1960年代後半にかけての「箱根山戦争」は、日本の観光開発史における企業間競争の象徴とも言える「縄張り争い」として語り草になっています。
そして、2025年現在、再び箱根エリアでの両社の事業展開が注目されています。 インバウンドを中心とする旺盛な観光需要に照準を定め、小田急と西武はともに、明確な経営戦略に基づき、箱根での事業展開の強化を構想しています。 小田急は「稼ぐ観光」を掲げ、新宿を観光ルートのハブ(拠点)とし、箱根や湘南といった地域で観光客を誘致する構えです。 一方、西武もリゾート開発を本格化させることを成長戦略として掲げており、両社の狙いは「インバウンドの囲い込み」にあります。
このように、箱根をめぐる両社の競争は、利用者にとっては新たなサービスや施設の充実、利便性の向上といった形で還元される可能性を秘めており、今後の動向から目が離せません。
—
まとめ
2025年の小田急は、まさに変革の時を迎えています。 3月のダイヤ改正による特急ロマンスカーの増発や停車駅の見直しは、通勤・通学の利便性を飛躍的に向上させ、乗り換えのストレスを軽減しました。 特に、多摩線沿線の方々にとっては、都心へのアクセスが格段にスムーズになったことは、日々の生活に大きな変化をもたらしていることでしょう。
そして、4月15日から始まった「ロマンスカーの子育て応援車」の運用は、子育て世代の移動に対する不安を和らげ、より多くの家族が安心して小田急線を利用できる環境を整備しました。 マスコットキャラクター「もころん」の人気も相まって、小田急の「子育て応援ポリシー」は沿線全体の魅力向上に大きく貢献しています。
総額436億円を投じる2025年度の設備投資計画は、鉄道施設の耐震補強やホームドアの設置、新型車両の導入といった安全対策とサービス向上を両立させる小田急の強い意志を示しています。 これらの見えない努力が、日々の安全で快適な運行を支えているのです。
さらに、2025年秋以降に拡大されるクレジットカードやデビットカードによるタッチ決済、そしてEMotデジタルチケットのQR認証は、国内外の全ての利用者にとって、よりスマートでストレスフリーな移動体験を実現します。 特に増加するインバウンド観光客にとっては、言語の壁や現金準備の煩わしさから解放される、まさに「神サービス」となるでしょう。
これらの取り組みは、単なる交通機関としての役割を超え、小田急が「沿線の生活価値創造企業」へと進化を遂げていることを強く示しています。少子高齢化や労働人口減少といった社会課題、そしてインバウンド需要の増加といった市場の変化に対応しながら、小田急は「安全」「安心」「快適」なサービスを提供し続けることで、沿線に住む人々や訪れる観光客にとって「選ばれる沿線」としての地位を確立しようとしています。新宿の再開発、新型ロマンスカーの登場、箱根の新たな観光スポットの創出など、小田急の未来への投資は止まることを知りません。 今後も小田急の動向から目が離せないでしょう。